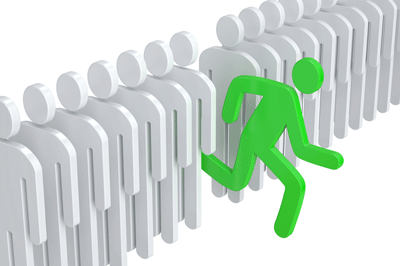- Home
- 建設業は発想の転換が必要
- 2.日本の建設産業構造はどうやってできたか
2.日本の建設産業構造はどうやってできたか

日本の建設産業の特徴に、重層構造と言われるものがあります。
ひどい場合だと5次下請けなんて話もあります。
重層構造が形成された原因は、いくつかありますが、過去の需給構造によるものが大きいです。
この10年の市場の縮小ばかりに目が行きますが、1978年から10年で建設市場規模は約2倍に増えています。
さらに言えば、戦後から90年代後半までの数十年に渡ってほぼ右肩上がりの時代がありました。市場が毎年拡大し、供給が追い付かない時代です。
建設分野だけでなく、日本社会全体がそういう状況でした。
また、公共工事分野においては指名入札、完成保証人制度により新規参入に障壁もありました。
このような、需要超過の時代、自社で10億の施工能力しかなくて、20億の業務の依頼があったらどうしますか?
普通は仕事を断ることはしません。20億の仕事を受けて、下請けを探して工事をやりますよね。
この時代は工期通りに完成させる施工能力が重視されました。そのためゼネコンは、下請けを囲い込み、協力会を組織し、施工能力を確保してきたのです。
さらに下請け業者が、その孫請けを探して、囲い込んでと、このようなことが、日本中で行われて、今の重層構造が出来上がったわけです。
この重層構造、ようは途中のピンはね層が多いため、建設コストが割り高になります。
また、実際に現場で施工やマネジメントをしている人の労働条件が悪化しています。
かつて日本の卸・小売業も重層構造でしたが、現在は崩壊しています。
建設業において、今後、これまでの枠組みが崩壊していくことを留意すべきです。